星雲・星団・銀河を見る
これは標準レンズで写した写真です。
有名な星雲・星団が見えていますね わかりますか?
正解は、↓↓この写真をタップしてね(マウスを乗せてね)
このように、肉眼でもぼんやり見えるものもありますが、ほとんどは暗くて、望遠鏡が必須だといえます
「星雲」とは

「星雲」とは宇宙空間に漂うガスや宇宙塵が集まったものです。
宇宙空間には星間ガスと呼ばれる水素やヘリウムの気体が漂っていたり、宇宙塵と呼ばれる星の残骸やデブリの欠片などが漂っていますが、それらが重力にとらわれると核となる物質の周囲に集まります。

そうして重力にとらわれた星間ガスがプラズマによって発光したり、光を反射している様子が煌めく雲のようにみえることから「星雲」と名前が付きました。
長い時を経て「星雲」がより高密度に大質量に集まると新しい星になると考えられています。
ちなみにM1かに星雲は、江戸時代に昼間でも輝いて見えた「超新星爆発」の残骸です
「銀河」とは?

「銀河」とは星やガス宇宙塵などの宇宙空間にある物質が巨大な重力によってとらわれてできている天体です。
地球は太陽の重力にとらわれて太陽の周りを回っていますが、「銀河」も同じように超大質量ブラックホールを中心に太陽のような恒星であったり地球のような惑星、宇宙塵やガスにダークマターなどが重力に捕われ漂っています。

「銀河」は宇宙空間に地球から観測できるだけでも数兆単位で存在し、太陽とその周りを周回している地球などを含む惑星を指す太陽系も、天の川を中心とする「銀河」の一部分に過ぎません。
ちなみにこのソンブレロ銀河は、ほぼ真横から見ているために、メキシコで近年まで広く用いられた、つばの広い伝統的な男性用帽子の形に似ているためこの名前が付けられました。
「星雲」と「銀河」の違い
「星雲」と「銀河」の違いは・・・
天体の一つでありなんらかの重力を持つ物質の周囲に宇宙ガスや宇宙塵が集まったものが「星雲」です。
「銀河」は太陽すらも比べ物にならないくらいの超大質量ブラックホールに恒星などの様々な星や「星雲」などの天体や、それ未満の宇宙ガスや宇宙塵などが集まってできている超巨大な天体になります。
大昔、天の川以外に空にモヤッとしたもの全般で「星雲」と呼んでいたそうです。
星雲という分類の中に銀河も星団も含まれていました。
私が小学生の時は「星雲・星団」と2分類でした。M42オリオン大星雲・M31アンドロメダ大星雲などと呼ばれていました。
なんとなく「モヤッ」としたものを星雲と呼んでいたようです。
時が経つに連れて、天体望遠鏡の大型化や観測機器の性能の向上が進んで天体の正体が詳しくわかるようになり、現在では天体の構造などによって、「星雲」「銀河」「星団」と分けて呼ぶようになったということです。
「星団」とは
太陽のような恒星が、たくさん集まったものです。星団の場所や星団をつくる星の状態などにより、星団は2つに区分されます。
散開星団

10個から500個くらいの比較的まばらな集まりで、若い星たちで形成されています。
肉眼だけでも、星が分離できるものや、ぼんやりと星雲状に見えるものがいくつかあります。
おうし座のM45(すばる)や、かに座のM44(プレセペ)など、これまで銀河系内にたくさん確認されています。
球状星団

10万個から100万個ほどの星が球状に集まっている星団です。散開星団とは対照的で、年老いた星が集まっています。銀河系のまわりを、球状に取り囲むように分布しています。
肉眼でも見ぼんやりと見られるものが数個あります。
有名なものとして、いて座のM22、ヘルクレス座のM13、南半球で見られるケンタウルス座のオメガ星団があります。
「メシエ番号」と「NGC番号」について
星団、星雲、銀河をまとめたいくつかのカタログのうち、代表的なものとして「メシエカタログ」と「NGCカタログ」があります。
それぞれのカタログで付けられた番号が、星団・星雲などの名前として使われています。
例アンドロメダ銀河の場合
・メシエカタログでは31番→「M31」・NGCカタログでは224番→「NGC224」
■メシエカタログ
フランスの彗星捜索家として有名なシャルル・メシエ(1730~1817)が、見た感じが彗星と紛らわしい天体をまとめ、1771年に作成したカタログです。
カタログに記載されている天体を「メシエ天体」といい、29個の球状星団、27個の散開星団、7個の散光星雲、4個の惑星状星雲、35個の銀河など計110個(うち不明のものあり)が登録されています。
小口径双眼鏡・望遠鏡で楽しめる星雲星団カタログとして有名です。
■NGCカタログ
メシエカタログが作成されたあと、時の流れと共に天体望遠鏡の口径が大きくなったり、観測機器の性能が良くなり、より暗い星雲星団まで観測できるようになるりました。そして、メシエカタログだけでは足りなくなってきましたために、ドイツ生まれのイギリスの天文学者であるハーシェルが1864年に作成した星表に、デンマークの天文学者ドライヤーが新たな天体を加え、1888年に発表したカタログです。7840個の星雲・星団・銀河が登録されています。
「New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars」のカタログ名の略から「NGCカタログ」と呼ばれています。
メシエカタログ 78番
なんといってもオリオン座の西にある【M78星雲】
ヒカリの国といえばウルトラマンの故郷です
しかし、とても淡い星雲なので、小さな望遠鏡では見つけにくいです。

望遠鏡を使って星雲を見る
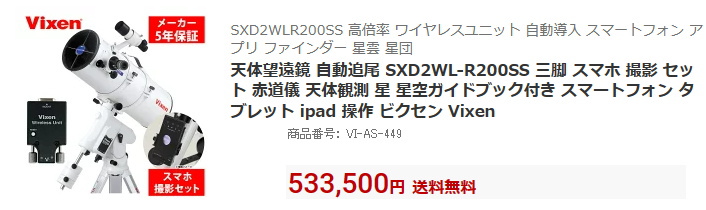
高価な機械(50万円超)を使えば、星雲・銀河・星団を自動で望遠鏡を動かして視界の中心に見えるようにして、地球の回転に合わせて自動的に追尾する事ができます。
スマートフォンを使ってワイヤレスで望遠鏡を動かして、スマートフォンで写真撮影できます。
う~ん 簡単すぎるし便利すぎる~~~でもそこまでお金かけたくないなぁ (#^^#)
昔は星空の地図(星図)とにらめっこしながら、この辺りにあるはずなんだけどな~ なんて言いながら接眼レンズを変えながら探しました。なので最近はとても便利ですね。
望遠鏡を覗いて見える星雲

大きな期待をしてはいけません。
大型望遠鏡や宇宙望遠鏡を使って撮った画像をプロが何枚も重ねて作った写真は、さすがにきれいいです。
でも、望遠鏡を通して見える星雲たちは【ほぼ雲】のような感じに見えます。しばらく見つめているとその雲の形がしっかりと見えてきます。
たとえば、この赤い「ばら星雲」ですが、望遠鏡で見つけた時は、その下側のような感じに見えました。(写真を加工しました)
小さな星の点と、周りにボヤっとしたものが有るような無いような・・・
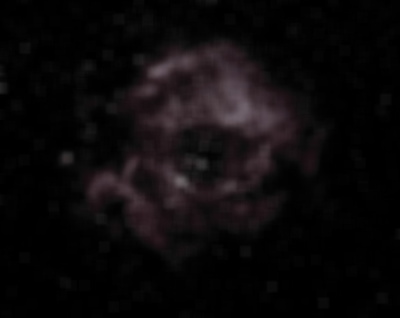
でも、がっかりする必要はありません。
しばらく見つめていると雲の濃淡が見えてきて、模様のついた雲を高精細写真と照らし合わせて想像する。
それだけで宇宙に対するロマンを感じたりできますね。
